O157の治療法は?初期症状は風邪に酷似?受診のタイミング
埼玉県・群馬県のポテトサラダが疑われる腸管出血性大腸菌O157による食中毒は
感染者がどんどん増えていっています。
さらには、先月横浜の焼き肉店で食事をした人からもO157が検出されたというニュース。
ここで、あれ??と思ったんです。
先月食事をしたのに翌月になってO157ってわかるの?
これは、初期症状でO157を疑っていないからなのか、
検査まで時間がかかっているのかな~と気になり
O157の初期症状や
O157と診断されたときの治療法などを調べてみました。
乳児、子供や高齢者など重症化しやすい人が家庭にいる場合は、
早く医療機関に受診することが大切です。
どのタイミングでO157を疑い、病院で受診したらいいのかのタイミングもチェック!
Contents
O157に感染するリスクは1年中どこにでもある!
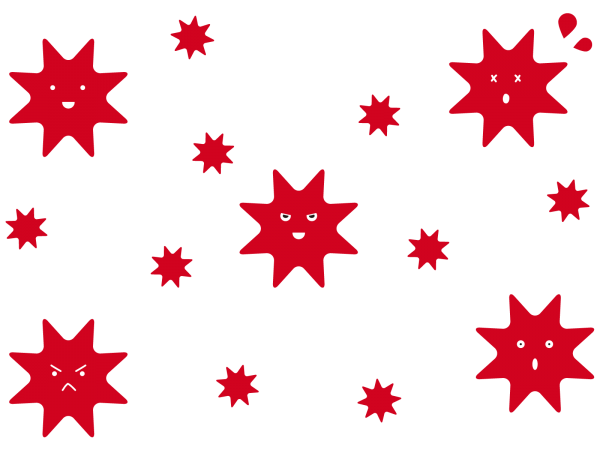
O157に感染するリスクは誰にでもあります。
O157の感染源は、スーパーで買ってきた食肉や野菜、漬物の場合もありますし、
幼稚園、小学生や中学生なら学校給食の可能性もあり、
過去にも何件も学校給食が原因のO157感染症が報告されています。
老人ホームの食事も過去にO157の発生事例がありました。
夏の時期であれば、過去に夏祭りでの冷やしキュウリや
仕出し弁当が原因のO157感染症の報告も少なくありませんね。
外食すれば、ステーキチェーン店、焼肉屋もO157の症例がありましたよね。
え・・・
どこで何を食べてもO157に感染するリスクがある??
そうなんです!!
あなたがたまたま食べたお昼のランチや、
子供が食べた給食、
夏祭りの屋台での飲食でO157を発症する可能性は0ではありません。
これってすごく怖いですよね。
O157の感染を防ぐには、O157が熱に弱いという弱点を持っていることを考慮すると
なるべく加熱された食べ物を食べるしかありません。
でも、この暑い時期に鍋料理食べたいですか?
やっぱり冷やし中華や、生野菜サラダだって食べたい!
ちょっと前に流行っていたジャーサラダだって
O157の感染予防という観点ではけっこうリスクの高い食べ物ですよね。
何を食べても腸管出血性大腸菌O157が自分にうつってしまうかもしれない!
O157の発生時期は6~8月が多いけれど、
低温にも耐えられるO157は冬であっても感染するリスクがあるんです。
本当にやっかいですよね!
O157に感染したときの初期症状は?胃腸風邪に似ている?

こんな症状がでたら、
やばい!O157に感染したかも?と疑ってみましょう。
医師によると、O157に感染したらこんな症状がでるそうです。
- 感染直後:症状は出ない
- 潜伏期間(4~9日):症状は出ない
- 発症1日目:おへそ周辺の激しい腹痛と下痢
- 発症3日目:出血性大腸炎(出血性下痢と激しい腹痛)
- 発症7日目:血小板や尿量の減少といった、溶血性貧血神経症状(HUS)
出血性下痢は血便ではなく、真っ赤な血が流れます。これらにあわせて発熱する場合もあります。また、初期症状は風邪とよく似ているため、注意が必要です。
O157に感染したときの例としてあげられていますが、
個人差があるのですべての人がこのような症状になるとは限りません。
O157の潜伏期間は4日から10日前後と幅がありますね。
この潜伏期間の長さがO157の発生源の断定を難しくしています。
10日前に食べたものって覚えています??
O157の初期症状としては、
- おへそのあたりの激しい下痢
- 水のような下痢
胃腸風邪や夏風邪で
腹痛や下痢になったりすることがありますよね。
O157の初期症状を風邪だと見過ごしかねないんですが、
O157の腹痛は、体をくの字に曲げるほど激しい痛みなんだそうです。
下痢はそれこそ蛇口から水がでるような
しゃびしゃびの水様便。
実は、O157に感染しても
- 無症状の人
- 軽い下痢えで終わる人
- 軽い腹痛で終わる人
もいます。
そういった無症状や軽い症状の患者からも
1~2週間程度は糞便からO157は排出されています。
ここで怖いのは気づかないうちの家庭内二次感染ですね。
O157に感染しても5~10日程度で自然治癒したり、
軽い人は下痢から1週間ほどでよくなることが多いそうです。
O157に感染が疑われる場合病院で受診するタイミングは?

激しい腹痛と水様便が見られたら念のため
医療機関を受診することが望ましいと思いますが、
ただの食あたりかも?と自宅で様子をみる人も少なくないかもしれません。
早めの受診でO157であることを早期発見したほうが重症化を防げるので
この腹痛は尋常じゃない!というときは病院に行った方がいいんです。
でも
O157かも??
と疑うべき決定打は血便。
O157の初期症状である
激しい腹痛と水様便の1~2日後に血便の症状がでるそうですが
このO147の血便は、
便にちょっと血がまじっているというレベルでなく
鮮血
トマトケチャップ
便器が真っ赤に染まるほどの血便。
もうこの時点で絶対にすぐに病院に行くべきです。
O157が重症化してしまったらどんな症状になる?
HUSは溶血性尿毒症症候群と紹介されることが多いですが
ここでは溶血性貧血神経症状となっています。
O157の重症化の例として、
神経障害や意識障害などがあるのもこのHUSの影響なんですね。
日本医師会によると
O157に感染した患者全員がHUSを発症するのではなく、
最大で全体の10%程度がHUSを発症くらいの確率で発症し、
そのうちの3%が死に至る。
O157に感染した人の6~7%はHUSを併発する化膿性があり、
血便が出た人はHUSの発症リスクが10%と高くなるそうなので
血便がでたら、必ず病院にいくべきです。
詳しい重症化の初期症状についてはこちらの記事にまとめています。
O157に感染した場合の治療方法は?
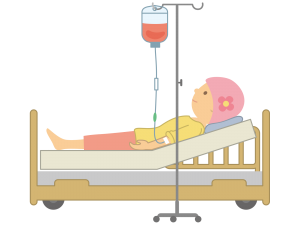
O157かも?と医療機関を受診したときに最初にすることは
検査です。
本当にO157に感染していた場合は、
体内でO157を増やさないために抗生剤の経口投与がされます。
抗菌剤の投与から3~5日で菌は消失するけれど、
抗菌剤を投与しても悪化するケースもあるそうです。
それでも、この抗生剤の投与は早期であればあるほど
HUSの併発率が低くなると厚生労働省は報告しています。
しかし、抗生剤の投与には賛否両論があるようです。
これまでにST合剤等を使用した場合にHUSが悪化したという症例や抗菌剤の使用の有無により臨床経過に有意な差異がなかったという研究結果が米国等で報告されていることから、欧米等には抗菌剤の使用に懐疑的な意見があり、世界保健機関(WHO)等においても検討課題として取り上げられている。また「抗菌剤が菌を破壊することによって菌からのベロ毒素放出が増加した」という試験管内での実験結果から、「患者への抗菌剤の使用は、腸管内で増殖した菌を破壊して症状を悪化させるのではないか」との理論的懸念も指摘されているが、臨床結果との関係は明確でない。
引用元http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0908/h0821-1.html#1-4
下痢止め薬はO157を体外に排出する妨げになるのでNGです。
自宅で下痢になった場合は、
下痢止め薬を自己判断で飲んだりしてはいけないですね。
抗生剤の投与と同時に水分の摂取で脱水症状になることを防ぎ、
安静にする。
場合によっては点滴をすることもあるそうです。
これがO157の基本の治療になるそうです。
O157感染症の特効薬や予防薬といったものはないんですね。
1996年の大阪 堺市のO157集団食中毒事件では、
9000人以上の患者が出たために
点滴用の台が足りなかったそうです。
それほどすさまじい下痢で脱水症状になるんですね。
まとめ
O157が重症化して併発するHUSは、
出血性大腸炎の症状、血便の症状がみられるとリスクがあがるということは
血便まで行ってしまう前に医療機関を受診し、
O157か検査をして、陽性であれば抗生剤の投与を早期に受ける。
それが大切かと思いました。
ちょっとした下痢で
O157では?と疑うのも不必要な混在を招いてしまうので
判断が難しいところです。
特に幼児、小児、高齢者はHUSのリスクが高くなるので
念のため早めに受診する方が安心ですね。
参考サイト:
https://www.med.or.jp/chishiki/o157/002.html
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0908/h0821-1.html#1-4